
大学受験料はいつ払うの?
どうやって?
どのくらいかかるかも知りたい
お子さんが受験期に入ると、避けては通れない『大学受験料の支払い』
巷では『平均で30万~40万はかかる』といわれる受験料に、気が気じゃない親御さまも多いはず。

平均って、みんなこんなにかかるの?
そこで、子どもの大学受験を経験した私が、大学受験料にまつわる疑問
☑ 大学受験料の額
☑ 大学受験料を支払う時期
☑ 大学受験料の支払い方法
まで、分かりやすくお伝えします。
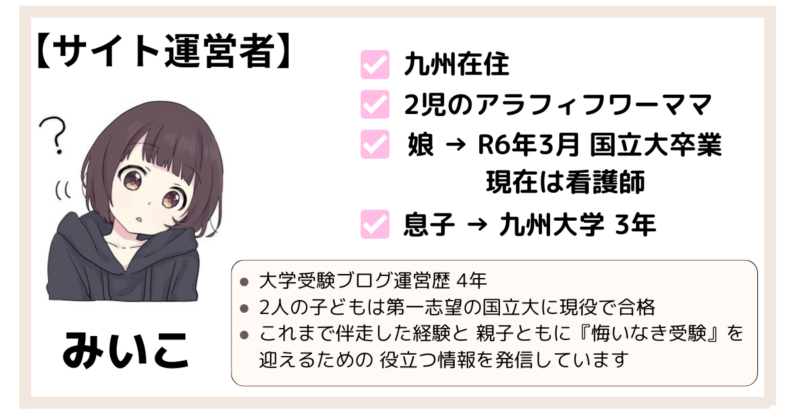
この記事をお読みいただくと
- 大学受験料についての正しい知識
- わが子にかかる大学受験料の額
- 受験料を少しでもおさえる方法
もわかります。

参考までに、娘の大学受験で実際に支払った額もご報告!
いざというときに慌てないよう、今のうちに『わが子にかかる大学受験料』を把握しておきましょう。
【2025 大学受験料】入学検定料は思ったよりかかる

大学受験料(入学検定料)は、何校受けるかによって金額が大きく変わります。

とくに滑り止めとして私立大学を受験する場合
受験料が想像以上にかかるのは『私立大の複雑な受験方式』も要因の1つです。
まずは基本の大学受験料からお伝えします。
R7年度 大学受験料(入学検定料)の額
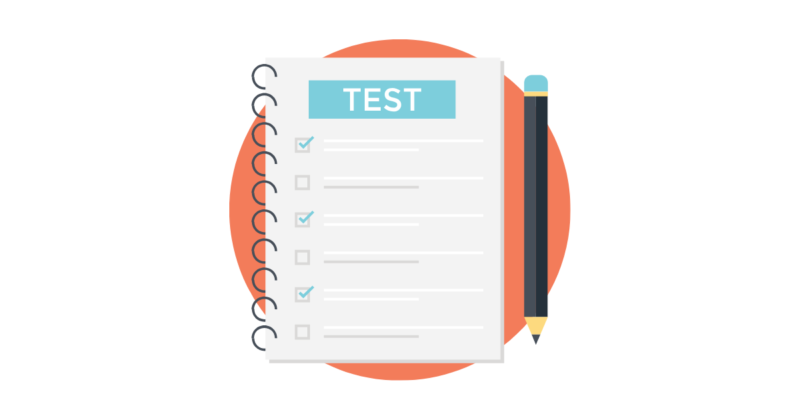
令和7年度 大学受験料(入学検定料)の額は以下の通りです↓
| 受 験 の 種 類 | 大 学 受 験 料 |
| 大学入学共通テスト | 3教科以上 18,000円 2教科以下 12,000円 成績通知を希望の場合+800円 |
| 国公立大学 | 1校につき 17,000円 |
| 私立大学 | 1校につき 平均35,000円 医学部等40,000円~60,000円 |
たとえば、国立大志望(前期+後期)で、併願大として私立大学を3校受験する場合↓
| 共通テスト | 18,800円 |
| 国公立大学 | 17,000円 × 2 = 34,000円 |
| 私立大学 | 35,000円 × 3 = 105,000円 |
| 合 計 | 157,800円 |
と、実際これだけかかります。
遠方の大学に受験であれば、受験料のほかにホテル宿泊費・交通費も必要。
宿泊費・交通費は、早めに予約すると『早期割』などで費用をおさえることもできます。

大学近隣・利便性のよいホテルは毎年『早い者勝ち』です。ご予約はお早めに
【大学受験料】現役合格めざすなら 『30~40万』は妥当かも

大学現役合格をめざすなら、大学受験料『30~40万』は妥当かもしれません。

絶対浪人したくない派は、受験料が高額になりがちです
国公立大なら『前期・中期・後期』と受験のチャンスは最大3回。
ですが中期試験を設ける大学は少ないため、多くの受験生は前期・後期で日程をくみます。
いっぽう私立大学は、試験日が重ならなければ何校でも受験が可能。
さらには
- 同じ大学・学部内でも複数の入試方式がある
- 大学独自で定める入試方法もある
など、私立大学は受験方式が複雑です。

利点としては、同じ大学を複数回受験すると合格率も上がること
受験料も個別に受験するよりは安いですが『1判定ごと』に受験料はかかります。

お子さんと話し合い、的を絞った受験計画を立てることが大切です
【大学受験料だけじゃない】滑り止めの入学金

大学入学前の費用は大学受験料(入学検定料)だけではありません。
志望大の合格発表前に、おさえておきたい合格大の入学金支払期限がくる場合。
入学金まで支払わないと入学資格を失います

いわゆる合格取り消しです
国公立大志望の人は『1つでも滑り止めの私立をおさえる場合』がこれに該当します。

国公立志望で私立おさえは『入学金の支払いが確定する』ということ
その入学金、1校あたり20万~30万。
1度払うと戻ってくることはありません。

へたすると30~40万じゃ利かない可能性がありそう…
大学受験は入学後だけではなく、実際は入学前からまとまった金額が必要です。
このことから
わが子の大学受験にかかる費用はどのくらいなのか?
を事前に把握することが大切です。
【いつ払う?】大学受験料の支払いは『出願期間内』

大学受験料の支払いは『出願期間内』におこないます。
以下より
- 総合型選抜(旧AO)・学校推薦型選抜
- 共通テスト
- 一般選抜(2次試験 国公立・私立)
に分けてご説明します。
総合型選抜(旧AO)は9月・学校推薦型選抜は11月に支払う

年内に合否が決まる総合型選抜(旧AO)・学校推薦型選抜による大学入試。
出願時期については
☑ 総合型選抜(旧AO)➡ 9月以降
☑ 学校推薦型選抜 ➡ 11月以降
と、文部科学省で定められており、受験料の支払いも同時期におこないます。

詳細な出願期間は各大学で異なるので、入試案内等で確認です
出願時に受験料を払い終えたことを証明するため
☑ 収納証明書の一部を添付
あるいは
☑ 領収書を同封する
場合もあります。
出願期間も長くは設けられていないため、受験料の支払いは『早めに済ませておく』ことが肝心です。
共通テストはR6年9月2日~10月7日に支払う

毎年1月におこわれる大学入学共通テストの受験料払込期間は、9月初日~10月初めまで。
共通テストについては、『検定料の払込期間』が別に設けてあります。
令和7年度 大学入学共通テストの入試情報は以下の通りです↓
| 検定料の払込期間 | 令和6年9月2日(月)~10月7日(月) |
| 出 願 期 間 | 令和6年9月25日(水)~10月7日(月) |
| 試 験 実 施 期 日 | 令和7年1月18日(土)、19日(日) |
| 追・再試験実施期日 | 令和7年1月25日(土)、26日(日) |
検定料の払込期間は1カ月ちょっと。

少し余裕があるようで、実はありません
というのも、在校生の共通テスト出願等はすべて『学校側がおこなう』ため。
個々の書類に不備がないかチェック期間もはいるので、払込についても早期に済ませるよう言われます。
お子さんから払込書を受け取ったら、なるべく1週間以内に支払いを済ませましょう。
- R8年度 共通テストより 出願手続きが電子化されます
- 大学入試センターでは、令和8年度 大学入学共通テスト(令和8年1月実施予定)より出願手続きの電子化をおこなうことを正式に発表しています。これにより検定料等の支払方法も、従来の指定金融機関の振込みからオンライン決済に変わります。
また、これまで在籍校を経由しセンターに提出していた出願方法も、志願者本人が直接センターに提出することになります。
【2次試験 国公立大】R7年1月27日~2月5日に支払う

国公立大の受験料支払いは『令和7年1月27日~2月5日』の出願期間内。
ここで注意するのは『国公立大を前期・後期試験ともに受験する』場合です。
前期+後期受験の場合、受験料は前期出願時に同時に支払います。

前期・後期で大学がちがう場合は『前期出願のタイミング』で後期分も払います

「前期ダメだったから後期出願」じゃないのね
まちがえやすいのでくり返しますが、国公立大の出願期間は
『前期』『中期』『後期』すべて 令和7年1月27日~2月5日まで
『後期試験も前期試験と同時期に受験料を払う』ことを覚えておきましょう。

親御さまに知ってほしい『大学の願書』について。
お子さんの出願時に役立ちます↓
国立前期合格しても後期分の受験料返還なし

国立大学の前期試験に合格しても、支払った後期分の受験料は返還されません。
理由は
後期分を支払った時点で出願が完了し、入試準備が進められてしまうため
前期試験に合格し、かつ入学手続きをとると後期試験の合格判定から『除外』されます。

後期試験を受けなくなった場合も、欠席の連絡をしなくて大丈夫です!
【2次試験 私立大】各大学で支払いが異なるので注意

私立大学の出願期間は『各大学で異なる』ので注意が必要です。

大まかにいうと、12月中旬~1月下旬あたり
滑り止めとして複数受験する人も多い私立大学。
受験料の支払いは『各大学ごとの出願期間等を確認する』ことが重要になります。
またWeb出願においては
出願登録完了後 24時間以内 あるいは 48時間以内
と早期に払込を指示する大学もあります。

出願期間を過ぎると、いかなる理由があろうとも受け付けてもらえません
大学では受験時期になると、公式サイトで『受験生向けの情報』を公開しています。
受験のしくみを正しく理解するためにも、かならず『受験大学の公式サイト』を確認することが大切です。
【2025 大学受験料】入学検定料の支払い方法

以下より『共通テスト』『2次試験』それぞれの支払い方法をご説明します。
大学入学共通テストは銀行か郵便局のみ(ATM不可)
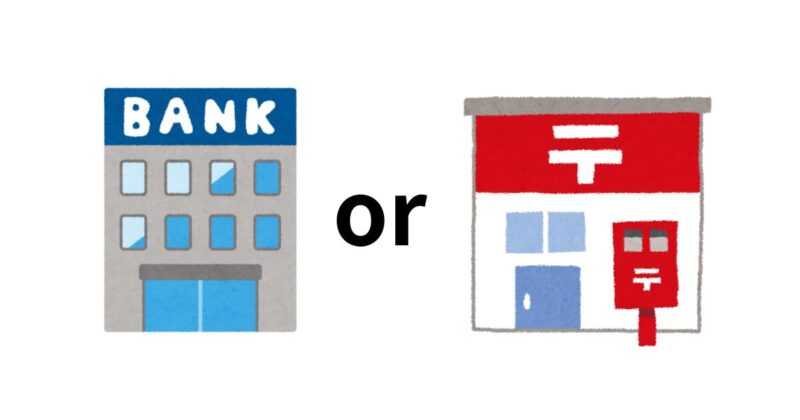
共通テストの払込方法は、『指定された銀行』もしくは『郵便局』の窓口で支払います。(ATM不可※)
※払込は受付局の日附印が必要です
かならず窓口でお支払いください

払込書は『受験案内』のなかに入っていますよ
- 志願票など出願に必要なものが入った重要な書類
- 現役生は学校から配布される(既卒生などは個人で取り寄せ)
- 令和7年度 受験案内は 9月2日より配布
令和7年度の共通テストは『変更点』がいくつかあり、大学入試センターの公式アカウントでも、以下のように発信しています↓
受験案内には主に、以下のことが載っています。
— 大学入試センター (@DNC_Japan) July 10, 2024
・令和7年度共通テストの主な変更点
・試験時間割
・出願方法、志願票の記入方法
・出願後の各種手続
・受験に当たっての注意事項等
これまでの試験からの変更点が多いので、予め、確認しておいてください。
詳細はこちら▼https://t.co/3hkxYfw71Q https://t.co/Jupv3dtmZV
受験案内の中にある『払込書』で受付窓口から支払ったあとは、その一部を志願票の所定欄に貼り付けます。

以下の『払込書イメージ』をご参考ください↓
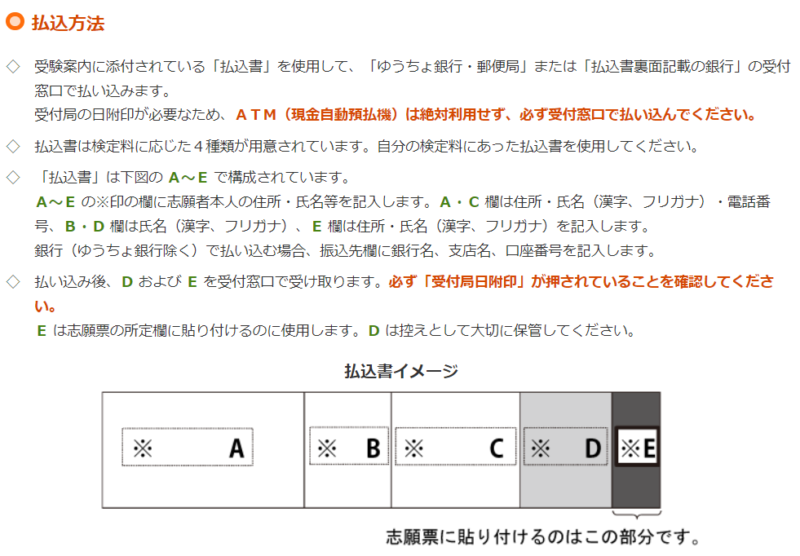
- R8年度 共通テストより 出願手続きが電子化されます
- 大学入試センターでは、令和8年度 大学入学共通テスト(令和8年1月実施予定)より出願手続きの電子化をおこなうことを正式に発表しています。これにより検定料等の支払方法も、従来の指定金融機関の振込みからオンライン決済に変わります。
また、これまで在籍校を経由しセンターに提出していた出願方法も、志願者本人が直接センターに提出することになります。
2次試験はクレカ・コンビニ・銀行ATM(ペイジー対応)など

Web出願の場合、2次試験の払込方法は
◎ クレジットカード
◎ コンビニエンスストア
◎ 金融機関ATM(ペイジー対応)
◎ ネットバンキング
などから選べます。

大学によって扱う種類が変わります
手軽にサクッと振り込みたい方は、私も利用した『セブンのコンビニ』がおすすめです。
レジで番号を伝えれば、支払いは即完了。

以下は息子にスクショでもらった画像
そのままレジの定員さんに見せました↓
- 支払い方法の選択は、お子さんの『出願登録時』におこないます。
『コンビニのセブン』を選択してもらい、あとから番号を聞いてください
その他『コンビニ』『銀行ATM(Pay-easy)』支払い手順はこちらです↓
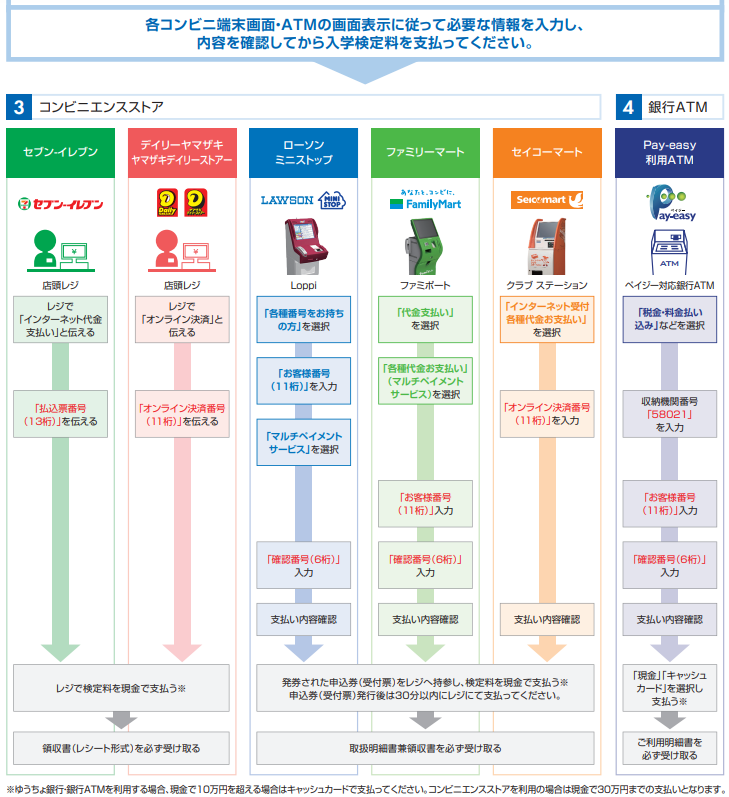
最後にお店でもらう明細書(レシート)等は『願書提出時』に必要な大学もあります。

いつものクセでポイっと捨てずに持って帰りましょう
【2025 大学受験料】入学検定料をおさえる方法3つ(注意点も)

大学受験料(入学検定料)をおさえる方法は3つあります↓
- 共通テスト利用入試の活用
- 学内・学部内併願の利用
- 地方試験会場の利用
以下より、注意点もふくめお伝えします。
①共通テスト利用入試の活用
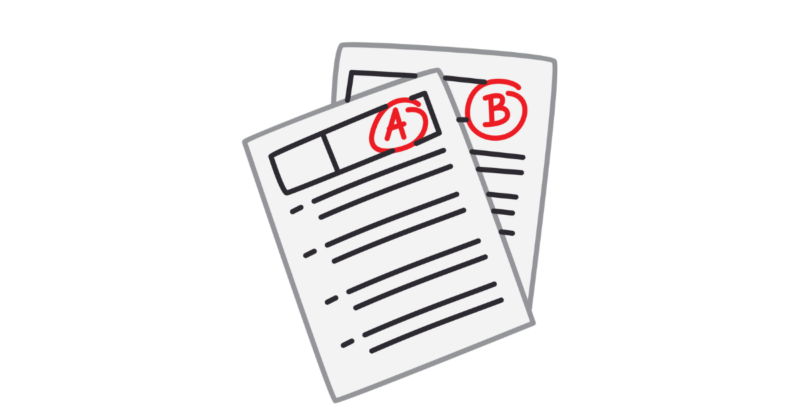
私立大学の受験料をおさえる方法の1つに『大学入学共通テストの利用入試』があります。

大学の個別試験を受験せず、共通テストの結果だけで合否が決まる受験方式です
通常は、1校あたり 35,000円ほどかかる私立の大学受験料。
この共通テスト利用入試を利用すると、1校あたり 15,000円~20,000円の受験料で済みます。

お得!
ですが、大学入学共通テスト利用入試にはメリットがある反面、デメリットもあります↓
【メリット】
◎ 受験料が安くなる
◎ 受験会場に行かなくてよい
◎ 複数の私立大も受験が可能
【デメリット】
◎ 個別試験と比べ募集人数が少ない
◎ 共通テストで高得点が必須
◎ 合格のハードルが高い
以上のことから、私立大学を確実におさえるには『個別試験もセットで受験する』ほうが賢明です。
②学内・学部内併願の利用

多くの私立大学で設けられる『併願割引制度』
『併願割引制度』とは、同じ大学で複数の学部学科を併願すると、2つ目以降の受験料が割引になる制度です。
例えば
単願 → 35,000円
2併願以降 → 20,000円(15,000円割引)
と受験料をおさえながら合格率を上げることもできます。

『ここは絶対合格したい!』という大学なら、ぜひ利用したいところ
併願割引制度で気をつけたいのは
大学により割引率や出願方法も異なる
という点。
受験候補の大学は、早めに大学の公式サイトなどで確認することが大切です。
③地方試験会場の利用

受験大学が遠方でも積極的に受験できるよう、地方の各主要都市に受験会場を設ける大学もあります。

子どもの体力やウチの経済面からも、うれしい制度ね
当然ですが、遠方の受験大学に別会場がない場合は、現地へ向かうしかありません。

大学受験の付き添い、お子さんの大学1人暮らしをお考えの方はご参考ください↓
遠方大に受験の場合、親の役目としてやるべきことは『宿泊先の確保』

ホテル予約は、好条件のところからなくなります

早めの予約が肝心ね!
大手旅行会社が企画する、受験生のための宿泊プラン『受験生の宿』が毎年好評です。

受験生に配慮したサービスが人気
照明器具・机・加湿器なども無料で貸してもらえます
『受験生の宿』はオンライン予約です。
大学近隣・利便性のよいホテルは早期満室となるため、早めに予約をすませましょう。
- JTB 【受験生の宿】
安心の国内最王手 - じゃらんnet 【受験生の宿】
ホテル掲載数も多い - 楽天トラベル
楽天ユーザーおすすめ - るるぶトラベル 【受験生の宿】
画面も見やすく検索しやすい - 近畿日本ツーリスト【受験生の宿】
土地勘がなくても探しやすい - 日本旅行【受験生の宿】
『JR・新幹線+宿泊』も充実 - Yahooトラベル
最大10%お得になるPayPayポイント付与
大学受験のホテルについて、くわしく書いた記事です↓
【わが家の大学受験料】娘の大学受験で支払った額

国立大を卒業し、現在 社会人1年生の娘。
大学受験時に支払った実際の額がこちらです↓
| センター試験(現 大学入学共通テスト) | 18,800円 |
| 国立大学(前期) | 17,000円 |
| 公立大学(後期) | 17,000円 |
| 私立大学 1校 | 42,000円(共テ併用 含) |
| 専門学校 1校 | 20,000円 |
| 行かない大学等の入学金(2校) | 100,000円+270,000円=370,000円 |
| 合 計 | 484,800円 |
入学検定料だけとみると、115,000円くらい。
『私立大を複数受験しなかったこと』で、入学検定料は安くおさえられました。

ただ支払期限の関係上、行かない2校に入学金を納めることになったのはイタかった…
娘の大学受験でわかったことは
- 大学受験校・受験数は吟味する(やみくも受験はNG)
- 私立大など、1校でもおさえると入学金を払うことになる
- 私立大の合格発表日、入学金支払期限は大学ごとに要チェック など
受験直前期は、普通に『数万単位』でお金が飛んでいきます。

若干、金銭感覚がおかしくなる
受験生本人も、この時期はとくに勉強のことで手いっぱい。
かかるお金のことまで頭が回るはずがありません。
大学受験を目前にして、親ができることは
わが子の受験に関する費用・支払期限をしっかり把握すること
子どもからの情報だけではなく『親御さん自ら情報を集めること』が大切です。
【2025 大学受験料】支払う額・時期・方法 まとめ

大学受験料の額・支払い時期・支払う方法など、自身の経験もふまえてお伝えしました。

サクッと以下にまとめます
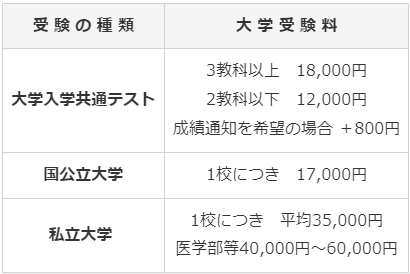
【大学受験料は出願期間内に支払う】
・総合型選抜(旧AO)・学校推薦型選抜の場合
→ 総合型選抜(旧AO)は9月以降
→ 学校推薦型選抜は11月以降
・共通テストの払込期間は9月初日~10月初
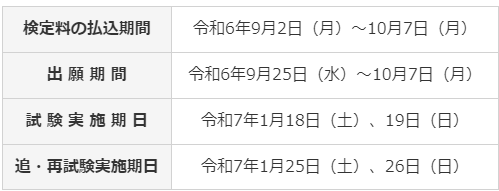
・2次試験(国公立大・私立大)の場合
→ 国公立大はR7年1月27日~2月5日の出願期間内に
→ 国立前期合格しても後期分の返還はない
→(注)私立の出願期間は各大学で異なる
【大学受験料の支払い方法】
→ 大学入学共通テストは銀行が郵便局のみ(ATM不可)
→ 2次試験はクレカ・コンビニ・銀行ATM(ペイジー対応)など
→ おすすめはセブンのコンビ二
【大学受験料を抑える方法と注意点】
・共通テスト利用入試の活用
→ 1校につき15,000円~20,000円と安くおさえられる
→【注意点】個別試験と比べて募集人数が少なく、合格のハードルが高い
・学内・学部内併願の利用
→ 同大学で複数の学部学科を併願すると、2つ目以降の受験料が割引になる
→【注意点】大学ごとに割引率や出願方法も異なる
・地方試験会場の利用
→ 受験大学が遠方の受験生に、地方の各主要都市に受験会場を設けている
→【注意点】遠方の大学に別会場がない場合は、現地へ行って受験する
大学受験料などの受験費用は、思った以上にかかります。
お子さんの受験する大学が
☑ どこで
☑ 何校あり
☑ どのような方法で受験するのか
によって、金額が大きく変わるのも事実です。

この記事が『大学受験に関する親御さまのお悩み』を少しでも解決できますように
そして、親子ともに『万全の態勢』で受験本番を迎えれるよう、心から願っています。
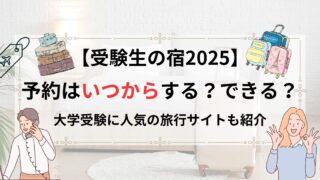
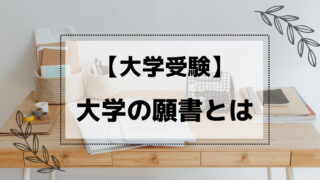
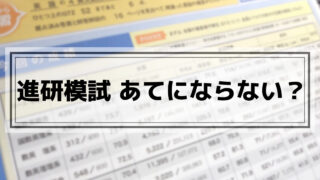
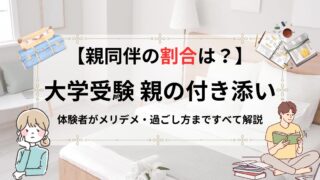
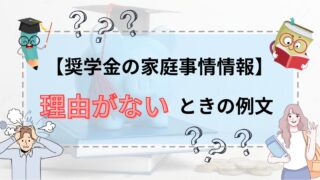
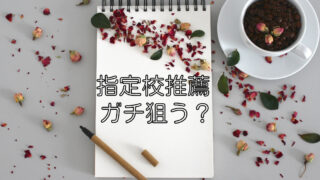
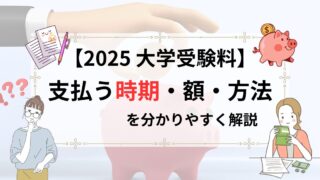
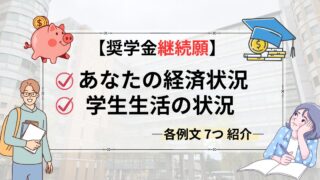
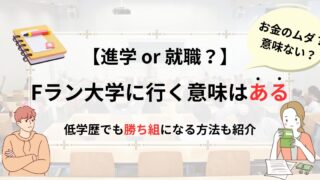
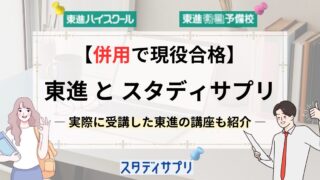
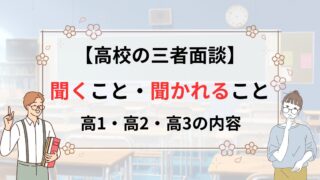
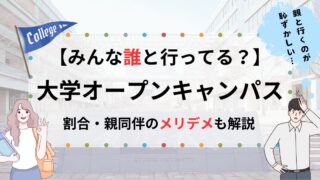
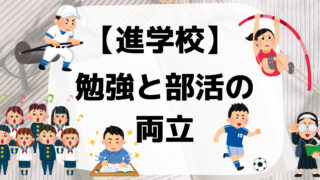
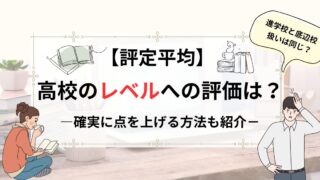
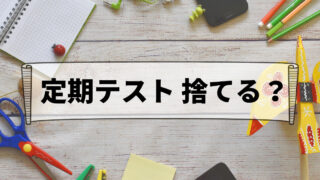
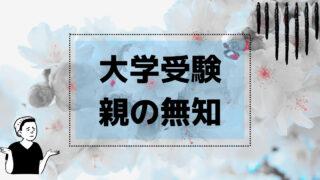
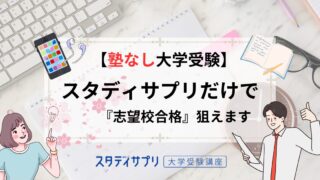
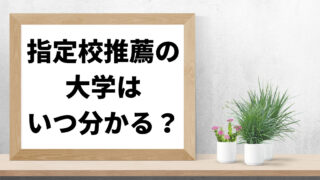
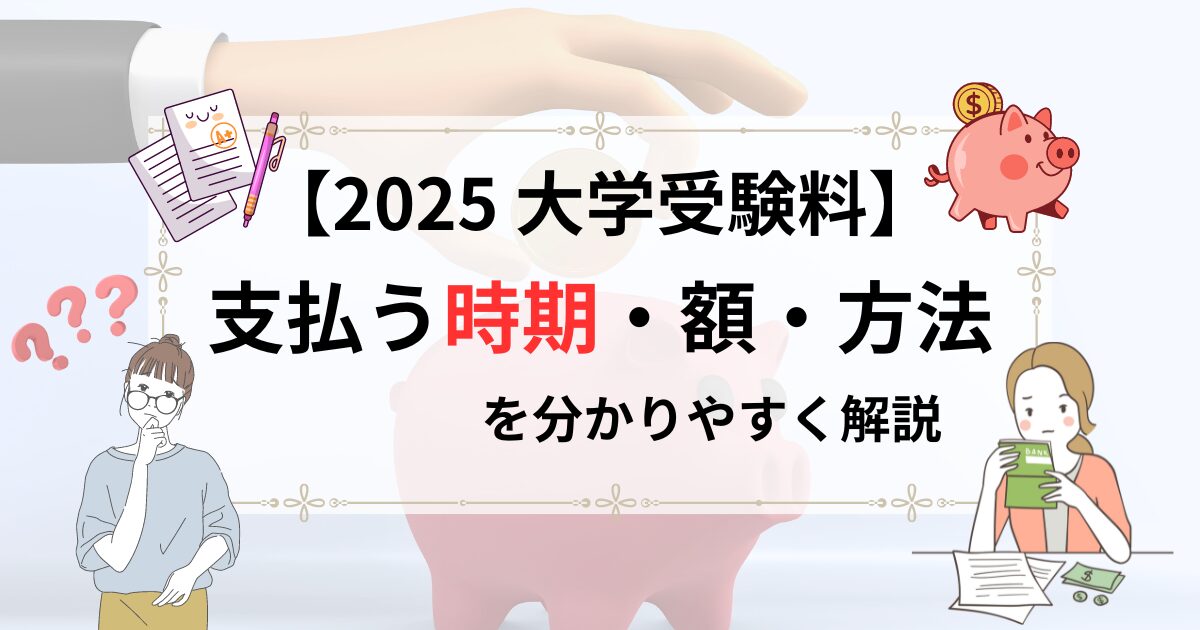
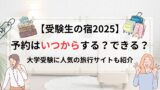
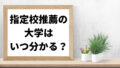
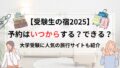
コメント